ビッグコミックスペリオールにたまに載ってたオムニバスシリーズ「HUMANITAS ヒューマニタス」が単行本になったので、やったーと思って買って読んで、めっちゃ面白いなー!とか思っているので、その話を書きます。
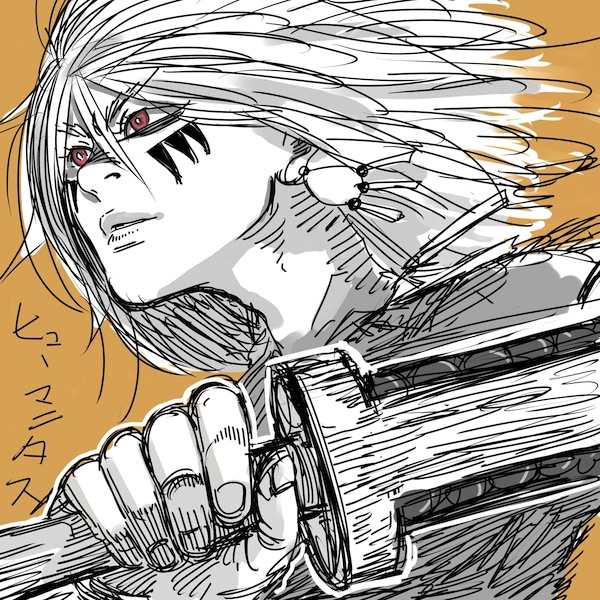
ヒューマニタスの単行本は、3つの話で構成されており、それぞれ「15世紀のメソアメリカで生まれた双子が殺し合わされる話」「ソ連時代に国を背負って戦うチェス選手の話」「遭難した白人男性がイヌイットの女性に助けられた話」です。その3作に共通するのは、登場人物たちのそれぞれが、彼らの置かれた環境の中で、彼らの感性において最善を尽くしたという話だと思います。そして、彼らの感性は、今とは時代も場所も環境も異なるため、今のこの場のこの環境、つまり、現代の日本の都会の常識からすると、ある種の不可解とも思える感性による選択のように見えるかもしれません。
その不可解さを否定してしまう自分の常識と、それでも彼らが生きてなしたことに対する賛辞の相反するような気持ちが胸の中に渦巻くのが本作の面白いところだと思います。あと絵がめちゃ格好良くて可愛くて美しくていいですね。めっちゃ好きですね。
単行本の後書きにおいて、ヤノマミ(南米の先住民族)を取材したテレビ番組を見たこと(具体的には書かれていませんがおそらくそう)が本作を描くきっかけとなったと書いてありましたが、それは個人的にとてもガッテンがいく話で、なぜなら僕も似たような割り切れなさ、単純な答えの出せなさを以前同じ物について抱いたからです。
ヤノマミは子供を産むと、それを育てるか、精霊に還すかを選択します。精霊に還すとは、生まれたばかりの子供をバナナの葉でくるみ、シロアリの蟻塚に置き去りにするということです。シロアリに食べられたその子供はもちろん死ぬことになります。これは嬰児殺しであり、少なくとも現代の先進国の常識としては犯罪に分類されることです。しかし、これが彼らの常識です。
文明がもたらしたもののひとつに人口密度の過密化が可能になったというものがあります。もし、原始的な狩猟と採集が主な生活であれば、一定地域に住むことが可能な人数は低いままでしょう。なぜなら、そこに自然に生み出される食べ物や安全な場所などには限りがあり、人数が多いことは住む場所や食料の取り合いによる争いを招く危険性があるからです。人間の数の調整は、原始的な生活における知恵とも言えるのではないでしょうか?少なくとも彼らはその方法で今まで上手くやってきたのでしょう。
彼らの行為は我々の常識からすれば犯罪的行為ですが、それを咎める権利は我々にあるのでしょうか?
もちろん、過去に存在した現在の常識では悪いとされていること(とはいえまだまだ存在はしていますが)、例えば人種差別や男尊女卑、身分による格差などを克服してきたのが歴史であり、その意味において、現代は過去の理不尽からすれば一番ましと考えたいものです。今がそれが良いということであったとして、では、過去の人々はみな不幸だったのでしょうか?それは「ある部分ではそうとも言える」し、「ある部分ではそうとは言えない」のではないかと僕は感じています。一概に全てを否定し得るほどに、僕は世界の正義というものを唯一無二の絶対的なものとして認識できていないからです。
人種によって役割が区別されることは悪いことですが、昔の物語に登場する、黒人の乳母と白人の少年の関係性にある種の幸福感を感じ取ってしまうことがあります。男尊女卑は否定されるべきものですが、昔の映画などを見て、女性は男を建てるものという古い常識の中に存在した、夫と妻の関係性に、良さを感じる部分が自分の中にないとは言えません。そして、それらの中にたとえ少しでも自分が良さを見出してしまうことに、自分の中の現代的で冷静な常識が否定的な見解を述べるのです。
常識で言えば正しいことは分かっているのです。しかし、自分の中にはそればかりではないということにも気づいてしまっています。
15世紀のメソアメリカで生まれた双子の少年たちは、彼らの部族の常識において、どちらか片方しか、生きる権利を得られず、互いに殺し合うことを運命づけられてしまいました。その戦いは無意味でしょう。僕の持つ常識で言えば、そんな戦いは最初からすべきではありません。
彼らの常識は作中でも疑われます。逃げ出して生き延びてもいいのではないかと。しかし、彼らの至った結末は、彼らの常識に寄り添った形で行われます。そして、そこには戦った彼らの姿があるわけです。それを読者としての僕は無意味なことだったとは思えないということです。
そこには「正しい」と「間違っている」が同時に存在しています。立ち位置の違いです。その両方の視点を同時に満たすいい感じの答え、つまり、ある種都合がよい答えが提示されるわけでもありません。
個人を犠牲にして国威高揚のために戦うチェス選手は、個を重んじる常識を背にして見れば、騙され搾取されていると思えるかもしれません。ただし、彼にも意志があるわけです。彼は何を大切にして、何のために戦ったのか、それが別の何かを犠牲にするものであったとしても、彼には大切と思えるものがあったのでしょう。それは本当に無意味でしょうか?彼は果たして国家に利用されていただけと言えるのでしょうか?
遭難した白人男性はイヌイットの生活に、ぎょっとしてしまいます。仕留めたアザラシの生の肉を口を血だらけにして食べること、彼らの持つ家族というものの考え方、それはイギリス人である彼が持ち合わせていたものとは異なるものでした。イギリス人である彼の常識は比較的現代の我々のものに近く、彼は読者の持ちうる違和感を、イヌイットの人々に対して表明します。
自然とともに生きるイヌイットたちの美しさと力強さに圧倒される彼は、ここで生きるのであれば、その中に自分も入らなければならないと思ってしまいます。そして、そう思ってしまったことは、人と人との間に、文化、慣習、常識などのように言い表すことができる、ただの個人を超えた巨大な壁があるように感じられてしまいました。なぜ世界中の人々の間にはこのような壁があるのか?その理不尽を感じてしまいます。
そして、それから長い月日を経て、彼の心に去来するものは一体なんであったのか?それは未読の人は読んでもらうとして、この断絶は、必ずしも理不尽ではないのではないかということに思い至ります。
世界には様々な環境があり、様々な状況があります。常識はそれらに合わせて生き延びることに最適化された形で構築されます。それゆえに、全ての人々の常識が完全に一致することはとても難しいと思います。
他の文化を尊重するということは、他の文化を全く異質と捉えて、壁を作り、干渉しないようにすることでしょうか?自分たちの文化の良さを広めることは、他の文化を破壊し、こちらの常識で塗りつぶすことでしょうか?どちらも、極端で、正解とは言えないのではないかと思っています。そして、絶対的な一意の解は未来永劫見つからないのかもしれません。
対立しうるのは、常識と常識、文化と文化かもしれませんが、その先端にいるのは人と人です。それぞれの人と人の背後にそれらがないということはないのだと思います。あらゆる常識はある状況では正しく、別の状況では間違っているのかもしれません。そして、その事実には常識が異なる他者がいて初めて思い至ることなのかもしれません。
ヒューマニタスを読んで、そういうことを思いました。