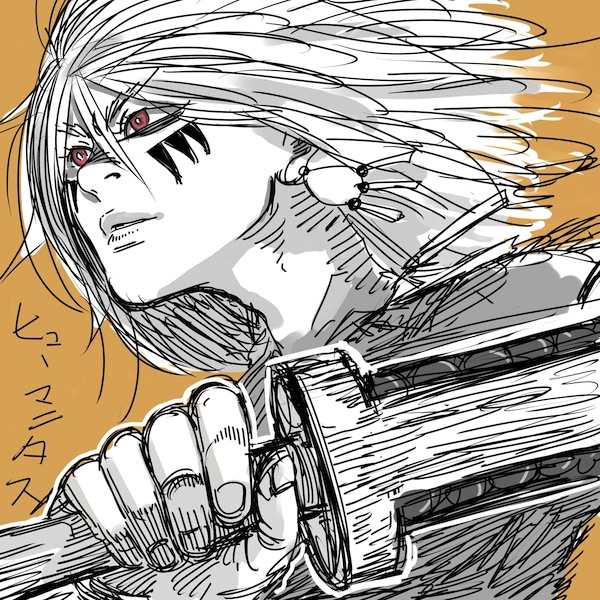主人公が成長する物語がすごく好きです。しかし、主人公が成長する物語は連載を長くは続けられないんじゃないかと思っています。なぜなら、人間は無限に成長するわけにもいかないからです。
それは肉体的な強さの成長でもそうですが、それ以上に精神の成長に関してそうだと思います。つまり、精神がどんどん成長してしまえば、人間としてどんどん成熟していきますし、成熟してしまえば、葛藤がなくなっていくんじゃないかということです。十分成熟した人間が主人公になると、困難に直面しても悩み苦しむことがなくなっていきます。それはそれでよいことでしょう。でも、物語としては描くことがなくなってしまうかもしれません。描くことがなくなってしまうと、その物語はもはや終わらざるを得ません。
長く続けば続くほど、よい物語というわけではないので、連載は終わって全然いいのですが、主人公の成長の有無によって継続できる長さの違いはあるのではないかと思いました。100巻を超えるような長く続く物語では、延々と主人公の成長を描くわけにもいかず、良くも悪くも主人公の成長要素はなくなっていきがちなのではないでしょうか?
例えば、先日200巻で完結した「こち亀」では、主人公の両さんの精神的成長はあまり見られません。いや、成長しているように思えるエピソードもあるんですが、だとしても、同じような無茶と同じような失敗を何度も繰り返し、その度懲りない様子が描かれます。もし、一回目の失敗で強く反省し、二度と同じような失敗を繰り返さない両さんであったとしたら、あのお話は数十巻も続いたあたりで描くことがなくなり、終わっていたかもしれません。
「ゴルゴ13」でも、デューク東郷は成長しません。ただし、こちらの場合は最初からある程度成熟していますし、物語が進めば進むほどに、その精神はより盤石です。ゴルゴ13の方式は、物語の主軸が主人公ではなく、彼に舞い込んだ殺しの依頼の方にあります。主人公は、主人公であるものの、それぞれのエピソードの中では脇役とも言えます。人間がぶつかる困難や、それを乗り越えた成長などは、それぞれのエピソードごとに登場した人物が担うことがあっても、デューク東郷自身が担うことはあまりない作りになっているはずです。
一方、主人公を成長させつつ長い物語を継続する方法としては、定期的に主人公を変更するという方法もあります。例えば、「ジョジョの奇妙な冒険」では、部ごとに主人公が交代することで、成長をリセットすることができています。新しく登場した主人公には新しい課題があり、それを乗り越えることがドラマとなるのです。
繰り返しますが、人間の精神が無限に成長していくと、それに反比例して人生の中から困難が減少していくのではないかと思います。困難が減少していくことはよいことですが、そこからはドラマがなくなっていくのではないでしょうか?完璧に完成した人間は、おそらくどんな困難に遭遇したとしても動じることなく淡々とそれを解決していくでしょう。だからこそ、その完成された人間以外に、困難を糧に成長する人材が必要になります。主人公は脇役に回り、その代わりに葛藤を主に担う人材が必要となるわけです。
「コータローまかりとおる」はまさしくこのような作りになっていたと思っています。「新コータローまかりとおる柔道編」では、前作で十分な精神的成長を遂げてしまった主人公のコータローは、狂言回しとしてある種の脇役に徹しており、その影響を受けた存在としての西郷三四郎や伊賀稔彦に焦点が当たっていた物語だと思いました。
柔道編におけるコータローの役回りは、他のキャラに対しての鏡のようなものです、コータローがいることで周囲の人々の姿の輪郭が浮き上がります。コータローは空手家でありながら、柔道の領域に足を踏み入れ、様々な事情で柔道の大会に参加してきた別の部活(アームレスリング部や相撲部など)との異種柔道試合において、相手の領域で相手のルールに従いつつ勝つということを繰り返します。相手の土俵で戦うことで、相手の個性を引き出し、そして破るということが繰り返されます。
この物語は柔道編を経て「コータローまかりとおるL」へとつながり、コータローの一族に関わる話として、再び話の焦点をコータローに戻して最終章という形式だったように思いますが、作者の健康上の理由から連載中断してもう随分になるので、続きが読めなくて残念です。
主人公が成長しない物語は、主人公の周囲にいる人々に変化を与え続けることで無限に続けることができます。探偵ものの物語もこの方式であることが多いですね。
であるがゆえに、物語が終結するときには、再び主人公にバトンを渡し、そこからのなんらかの精神的変化や、周囲の人間との関係性を変えることが終了の合図となりがちです。例えば、贋作専門のアートギャラリーを営む藤田を主人公とする「ギャラリーフェイク」では、助手のサラとの関係性が変化するようなエピソードをもって連載が完結しました。
その意味において、普段と何ら変わりない形で連載を終了した「こち亀」は特異な存在と言えるかもしれません。おかげで、いつでも再開しようと思えばできるでしょうし、次週のジャンプに何気なく載っていたとしても、ああ、そうかと思うだけです。
仮に、登場する全ての人間が完璧なまでに人間的な成長を遂げてしまった物語があったとしたらどうでしょう?それはどのような物語になるでしょうか?全ての人が分別があり、起きた出来事を淡々と解決していきます。それは面白いでしょうか?何らかの手法で面白く作ることも可能かもしれませんが、基本的には退屈のようにも思えます。
「青龍」という漫画には、ある文明を極限にまでに進化させ、人工的な精神的成長を達成した人々が出てくるのですが、彼らが直面したものがまさに「退屈」です。彼らは、自分たちを神として猿から進化させた人間を生み出し、それによって退屈しないドラマを生み出そうと試みました。
これはもしかすると、現実の人間もまた同じかもしれません。なぜなら、僕の生活は日々良い感じになっているからです。おかげで、昔のように金に困ったり、周囲の人間関係に悩まされたり、初めて手掛ける仕事が上手く出来なくて弱ったりを、なかなかしなくなってきました。
その僕がわざわざ漫画を読んでいるわけです。未成熟で、困難に直面しては葛藤し、それを乗り越えていく人々の登場する、漫画の中のドラマに一喜一憂しています。自分の成長が停滞してしまったことで、ひどく退屈しているからなのかもしれません。
自分という物語においても、無限に成長していくことができないなら、人生の道半ばで描くべきことが無くなってしまうでしょう。ただ、自分が十分成長したといっても、それはごく限られた分野での話です。新しい分野に手を出せば、またイチから始める必要があり、また継続的な成長が望めるかもしれません。もしくは、次世代の人材の育成を手掛けたり、困っている他人を助けるという主役を他人に回すのもよさそうです。あるいは、肉体の衰えや周囲の変化によって、新たな課題に直面させられることもあるでしょう。
人間が漫画と異なるのは、人気のあるなしに関わらず、いつ終わりがくるかが分からないことでしょう。退屈でも生きなければなりませんし、成長中でも死ぬかもしれません。
ともあれ、自分の人生が今成長物語なのか、成熟して他人の依頼を解決する物語なのかなどと考えてみるのも面白いかもしれません。成長物語は無限には続きません、なので、どこかで仕切り直す必要があるとか考えたりもします。成熟した物語は、何らかの外部を取り込まないと退屈です。退屈も過ぎれば、それを一旦捨てて、また成長物語に身を投じることもよいかもしれません。
とりあえず今はいる場所が比較的退屈になってきたので、漫画を読んで未熟な人々が頑張っているのを追体験したり、別の人を助けたり、気が向いたら新しい何かにチャレンジしてみようかとおもったりしています。